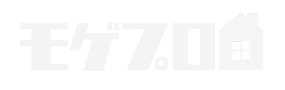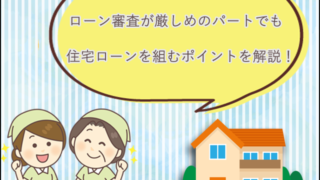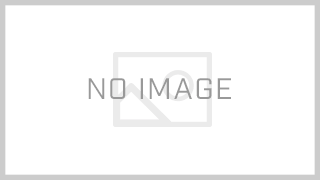住宅ローン控除の基礎知識
マイホーム購入を助けてくれる仕組みの一つに、住宅ローン控除があります。
わかりやすい言い方をすると、「一定期間に亘って、ローン残高に応じた金額を所得税から引いてもらえる」制度です。
一般的には、ローンの年末残高の1%を、毎年の所得税から10年に渡って引くことができるため、ローン残高が大きいと金額も大きくなり、非常に大きな節税効果が期待できます。
ただし、ここで注意点があります。所得税の額が控除額よりも小さいと、引き切れない金額は活用できなくなってしまいます。
例えば所得税が15万円、控除可能金額が20万円の場合、5万円は返ってくるわけではなく、有効活用できなくなってしまうのです。
この損を埋めるべく存在するのが、住民税の住宅ローン控除で、所得税から引き切れなかった金額を、その翌年の住民税から引いてもらえます。
なぜ同じ年の住民税から引かれないのかというと、住民税は前の年の所得税額を元に計算されるという仕組みがあるからです。
先の例を挙げ、所得税15万円、控除可能金額20万円の場合、20万円のうち15万円分は所得税から引かれ、残った5万円が翌年の住民税から引かれることになります。
住民税から引くことができる金額には上限があり、所得税と同じくその金額を超えて引くことはできない点には注意が必要です。
これらの仕組みの恩恵を受けるために、納税者側ですべきことは特にありません。
所得税の確定申告や年末調整できちんとした申告を行うことで、市町村が住民税を計算してくれますが、どれくらいの額を引いてもらえるのかは確認しておいた方がよいでしょう。
どんなときに控除が受けられるの?
住宅ローン控除は、住宅を購入したり新築したりすると対象になります。
しかし実際にはいろいろな条件が決められており、それをすべてクリアしなければ受けることができませんし、場合によっては控除を受けられない人も出てくるので、注意が必要です。
まず、対象となるローンが、住宅とその住宅が建っている土地を取得するためのものである必要があり、また、返済期間が10年以上であるというのも条件の一つで、10年以下の場合は対象外となります。
借入先も条件の対象となり、銀行、住宅金融支援機構、地方公共団体など、指定の機関からの借り入れでなければいけませんので、親族や知人からの借り入れは対象外となり、また、勤務先から借りている場合は更に年利1%以上であることが条件となっています。
面積も条件になっています。床面積が50平方メートル以上の住宅が対象となっており、事務所や店舗と併設している場合は、床面積の50%以上が住居用であることが条件です。
さらにローンを借りている人の所得合計金額が3,000万円以下である必要があります。
もう一つ重要な点は、入居しているか否かです。
住宅を購入、あるいは新築してから半年以内に入居し、そのままその年の12月31日まで継続して入居していることも条件です。
住宅ローン控除を受けるためには、不動産を取得した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
申告するときは、土地・建物の全部事項証明書、住宅ローンの年末残高証明書などの必要書類が必要になります。
こうすることで、会社に勤めている人は、2年目以降の年末調整のタイミングで控除を受けることができますが、自営業の人は、毎年の確定申告の際に申告する必要があるため注意が必要です。
新築住宅以外でも、控除が受けられる?
住宅ローン控除は新築住宅を購入、建築した際の仕組みですが、それ以外でもいろいろな条件付で控除が受けられる場合があります。
中古住宅を購入した場合は、新築住宅を購入した際の条件に加えて条件が付け加えられます。
例として、取得したタイミングにおいての建物の築年数が大切です。
マンションなどの耐火建築物の場合は築後25年以内、木造住宅などの非耐火建築物は築後20年以内でならず、これを超える場合は、地震に対する安全性の基準に合格するなど、建物の安全性を証明する必要があります。
さらに、取得先が配偶者や特定の親族ではないことも条件に含まれます。
建物の取得だけではなく、増改築した場合でも住宅ローン控除を受けることができる場合があり、自分が持っている住宅で、引き続き住み続けることや、増改築した建物の床面積が50平方メートル以上であることなどが条件です。
バリアフリー改修工事や、省エネ改修工事になどに関しても条件が定められています。
バリアフリー改修工事の場合、廊下の幅を拡張したり、階段の勾配を緩和するなど、指定された工事であれば控除の対象となり、省エネ改修工事に関しても、指定された一定の改修工事を行った場合、所得税を控除してもらえる制度が作られています。
対象となる工事は、窓の改修工事や、床や天井、壁の断熱工事などです。
住宅ローン控除制度は、頻繁に見直しが行われ、制度がコロコロと変わりますので、自分だけではよく分からない場合は、税理士や税務署の相談窓口などを利用するようにしましょう。